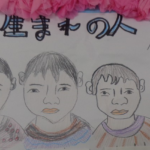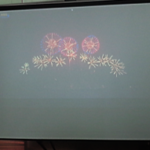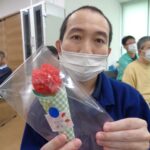夢工房みどりのモットーは
「心豊かに、そして働く喜び感じながら、地域で生活していくことを支えていきたい」
「誰でも自分らしく過ごせる『居場所』でありたい」です。
先日職員会議で「ダウン症のある人たちが集まるイベント」の動画を視聴し、eラーニング研修を行いました。とても明るい雰囲気で様々な取り組みが為されていましたが、その参加理由の中で「友達と会うのを楽しみに来ました」という言葉が多く聞かれました。
「ここに来たら安心できる友達や仲間と会える」ということは、お一人おひとりの居場所となるためにとても大切なことの一つかもしれません。
また、職員から「モットーの『喜び感じながら』という部分は利用者の方にとっても職員にとっても大切だ」と意見が出ました。喜びというものも大切にしたいですね。
そういうことを考えつつ、今回のきらりほっとです。
事業所では3つの班で活動しています。それぞれの班の中では仲間意識が高く、共に協力したり、思いやったりされている姿を目にします。
Aさんが何だか動きが硬いときがありました。「どうしたのかな?」と職員がつぶやいたら同じ班の仲間が、こうなんじゃないかなぁという理由を教えてくれました。その後Aさんに優しい言葉で次の行動を伝えてくれていました。仲間が伝えてくれることで、安心して動けていました。
Bさんは利用者の方同士だけでなく、職員も含め様々なところに気を配ってくれます。最近はその優しさを言葉にして伝えてくれることがさらに多くなっていて「いいこと、楽しいことばいっぱい考えんね。嫌なことは考えない!」と優しく鼓舞してくれました。その一言で頑張れます。
職員のことですが、Cさんが連休後勘違いして多く休まれたのですが、出勤前日に職員の終礼で「Cさんはとても真面目な方なので『どうして来なかったんですか~』という言葉をかけるとショックを受けるかもしれないので、休まれたことには触れずに話しましょう」となりました。大切な配慮だなぁと私がきらりほっとしました。Cさんはやっぱり気にはなっていたのか出勤後すぐに「ゆっくりしとったとさ~」と言われたようですが、雰囲気は明るかったようで、その姿にもきらりほっとしました。
事業所での時間は一日の3分の1の時間を占め、その時間が充実することは生活の中でとても重要だと思います。お互いの優しさや思いやりで、仲間感を感じながら喜びのある生活を送りあえていることを感じると、とてもとてもほっとします。